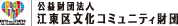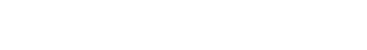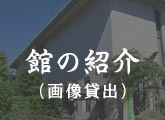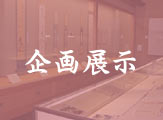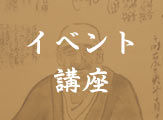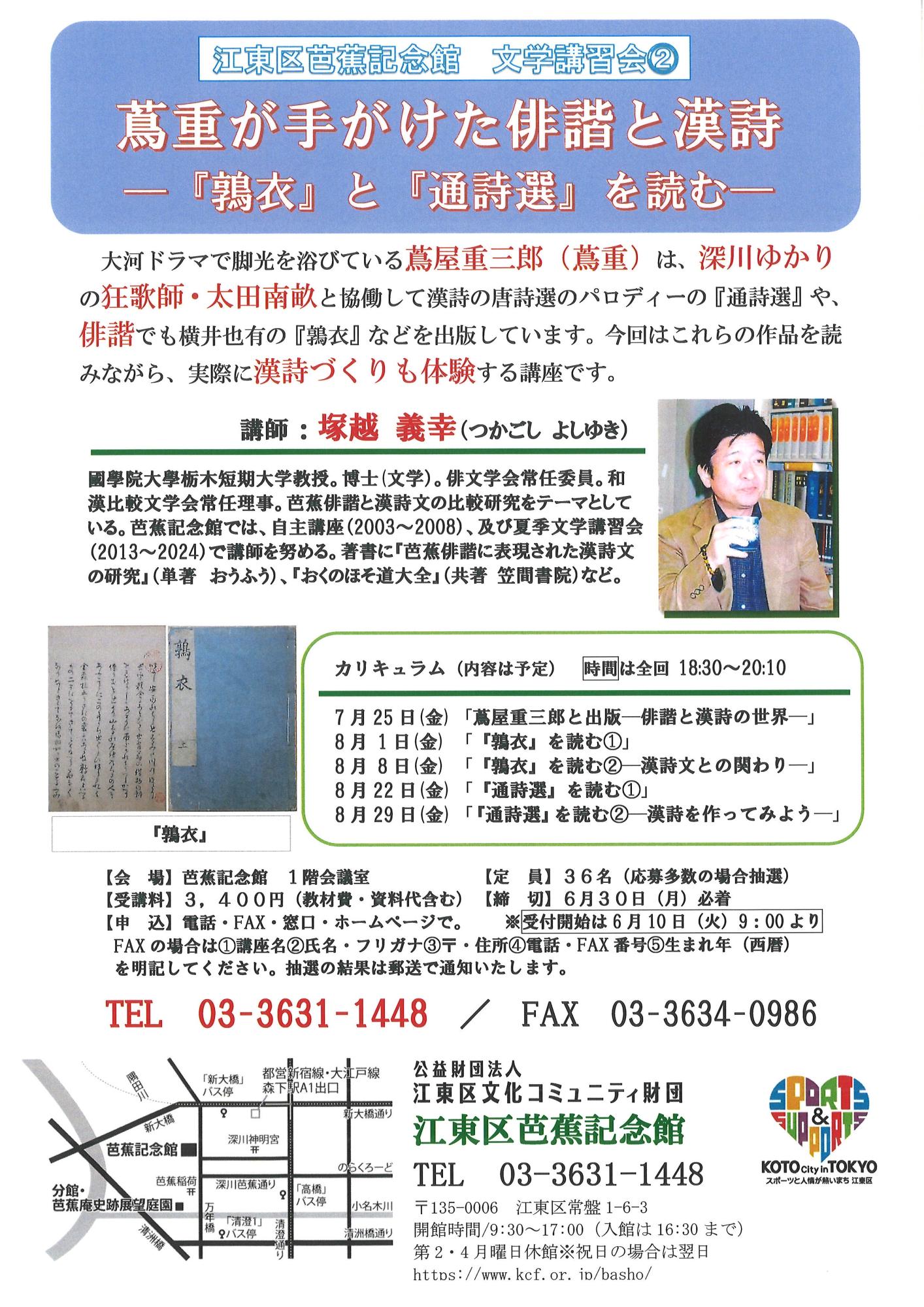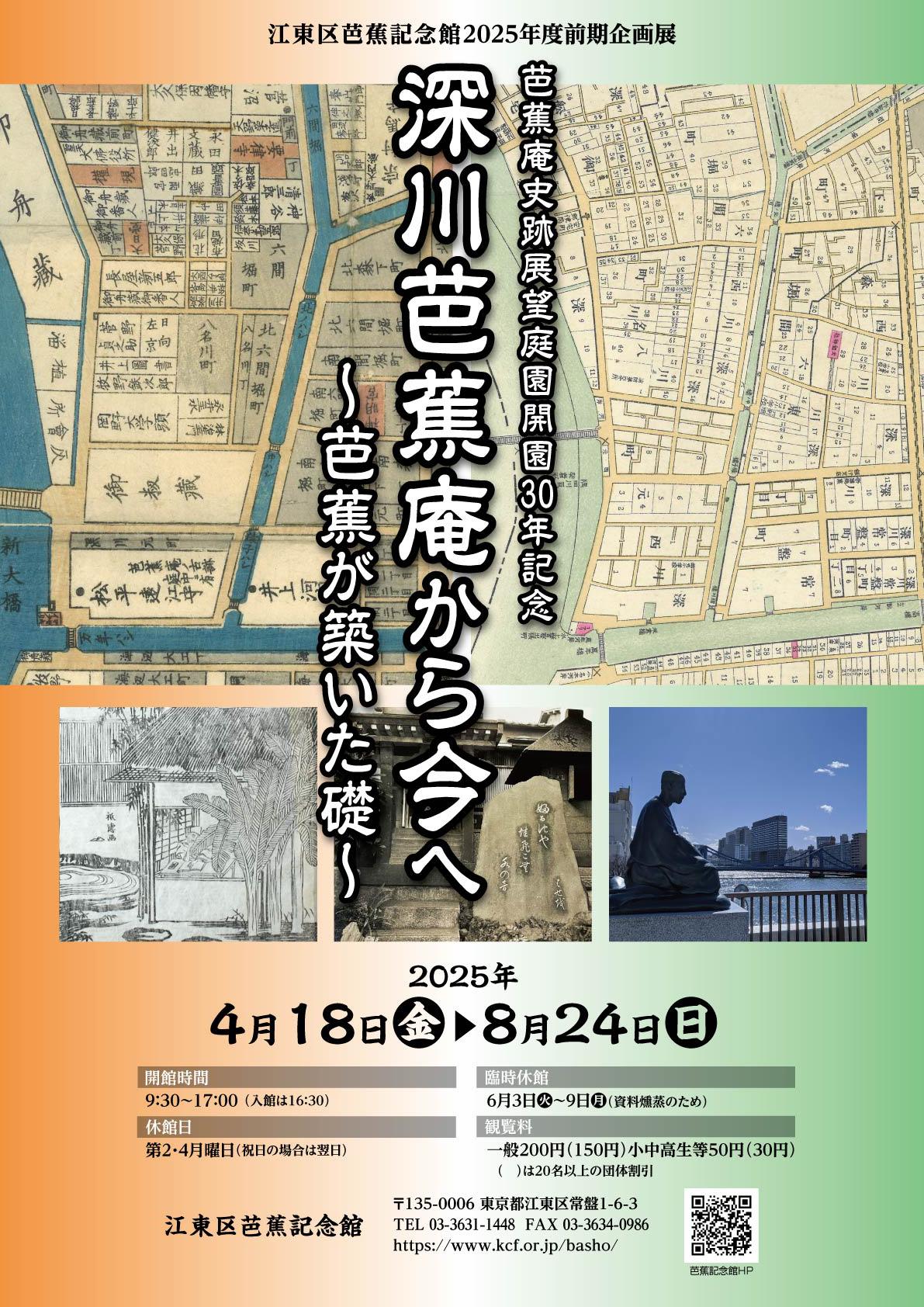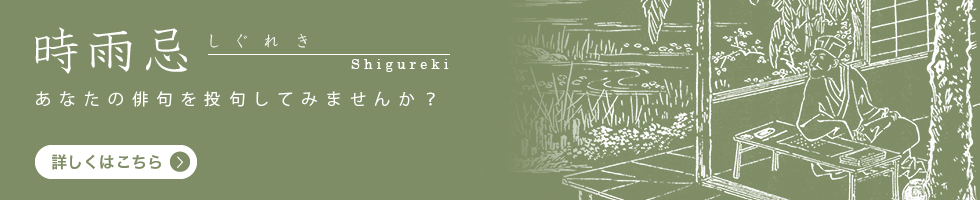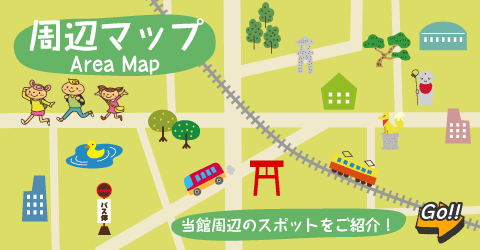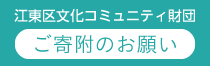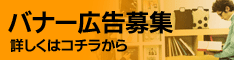お知らせ
- 2025年6月21日その他【選定結果】地域文化施設の英会話講座運営事業委託に係る公募型プロポーザルの実施について
- 2025年6月10日その他財団情報紙「カルチャーナビKOTO」6月号発行
- 2025年6月1日その他2024年度 芭蕉記念館投句箱入選作品決定!
- 2025年4月1日施設利用【2025年4月1日更新】施設利用料金の特例的措置に伴う差額還付について
- 2025年2月8日施設利用2月11日(火)以降、研修室の座卓・座椅子をセットで設置し、 ご利用いただきやすくなります。今後、既存の座卓もしばらくご利用いただけます。